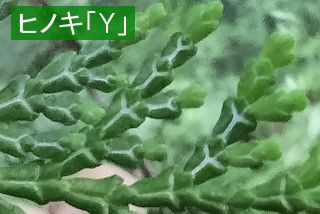いこまいけ高岡 >
砺波市 観光案内
頼成の森
県民公園 頼成の森(らんじょうのもり)は、1969年(昭和44年)5月に開催された第20回全国植樹祭を記念して、1975年(昭和50年)に開園した森林公園です。総面積115ヘクタールです。
標高70~200メートル、一辺が約 1.5キロメートルのおにぎり型(逆三角形)、全体的には北に 10%勾配で傾斜し(北から南に標高が高くなります)、変化に富んでおり、老若問わず自然観察を楽しめます。1985年(昭和60年)には「全国森林浴の森百選」、1988年(昭和63年)には「とやま花の名所」に選定されています。1986年(昭和61年)に第1回頼成の森花しょうぶ祭りが開催(当時は 80品種20万株、花しょうぶ園の面積は 0.8ha)されました。
頼成の森(写真:2024年5月3日 7時40分撮影)、森林科学館
頼成の森地図(Google Map)
住所:富山県砺波市頼成156
「頼成の森」の地形と地質
園内最低地点は標高 70メートル(国道359号線入口)、最高地点は標高 197メートル(ひよどり山)です。標高差はおおおよそ 130メートルです。富山県の大体の地形と同様に、北から南へ標高が高くなっています。
地質は「新第三紀の音川累層」、約500万年前の寒く浅い海に堆積した地層です。北陸堆積盆地(富山堆積盆地)と呼ばれているようです。園内では、南の標高の高い場所へ行くほど古い地層が現れます。通常、地層は「地層累重の法則」により、下のほうに古い地層、上へ行くほど新しい地層となります。頼成の森では、標高の高い場所で古い地層が見られることから「地層の逆転」が起きています?断層ずれと風化で新しい層が削れた?
園内では砂岩や泥岩の露頭があり、散策路は細かい砂の土壌により、やや滑りやすいです。地層や化石を観察できる場所が 3か所あります。
現地の説明板
No1 観察地
「鬼の洗濯岩」とも呼ばれる砂岩の露頭が見られます。頼成の森南東端付近、ヒヨドリ・トンネルから西へ100メートルの遊歩道路上です。走向N80W・傾斜20度。「走向」とは、断層が水平方向でどの方向に伸びているかを示すもの。「N80W」は北西80度(北から西へ80度)です。
鬼の洗濯岩(写真:2024年7月20日 14時02分撮影)
No2 観察地
砂岩泥岩互層、唐草ショウブ池近くの管理道「ヒヨドリ線」道路脇の崖(東側法面)に地層が露出しています。地層の中に。亜炭・貝化石(ホタテガイ、カキ)・火山灰(軽石)などを観察できます。走向N80W・傾斜18度。
砂岩泥岩互層(写真:2024年5月12日 13時07分撮影)
No3 観察地
管理道「栂野尾線」の東側法面、露出している地層で突き出ている丸い石「ノジュール(英語:Nodule、団塊)」を観察できます。ノジュールは化石や砂粒を核として、岩石中の石灰分が濃縮沈殿しながら固まってできた石です。砂岩や泥岩の中で、砂や泥が周囲の母岩(堆積物や堆積岩)より固い球状となって地層に含まれています。
ノジュール(写真:2024年5月3日 9時21分撮影)
天狗山
頼成の森の北縁・東寄り、ヒヨドリトンネルから続く遊歩道「緑のトンネル」を南東へ進むと天狗山(てんぐやま、標高 192.4メートル)があります。天狗山には二等三角点「天狗岳」があります。天狗山から南へは「ツツジのこみち」、東へは「見返りの坂」があり、その先には「見晴らしの丘」があります。なお砺波市には二等三角点が3か所あり、天狗山の他は「鍬崎(牛岳)」と「太郎丸(市街地)」です。
天狗山(写真:2024年5月3日 8時23分撮影)
ヒノキ(檜)とアスナロ(翌檜)
ヒノキとアスナロはともに「ヒノキ科」の針葉樹で、山地に生え、人工林として植樹されています。いずれも日本固有種、ヒノキはヒノキ属、アスナロはアスナロ属(アスナロ属はアスナロだけの一属一種)に分類されています。樹皮は赤褐色で、帯状に縦に裂け剥がれます。葉は鱗(うろこ)状です。
ヒノキとアスナロの簡単な見分け方は、葉裏の白い気孔帯を観察します。ヒノキは「Y」、アスナロは「W」となっています。
「アスナロ」の名前の語源は、ヒノキに似ているが材質が多少劣ることから「明日はヒノキになろう」を意味するとの説もあります。井上靖の小説『あすなろ物語』を思い出しますよね。
ちなみにヒノキ科ヒノキ属には「サワラ」があり、サワラの気孔帯は「X(エックス、蝶)」の形に見えます。そして、ヒノキ科クロベ属のクロベ(別名:ネズコ)は葉裏の気孔帯が緑白色で目立ちません。「クロベ」という名前の由来は、富山県では「黒部峡谷に多い木だから名づけられた」とか「クロベの木が多いから黒部になった」とか言われています。ただし全国的には、葉裏の気孔帯が緑白色で目立たないため、葉裏の色が暗く、木全体を見たときに黒っぽいから「クロビ(黒檜)」とよばれ、これが「クロベ」に転じたとされています。
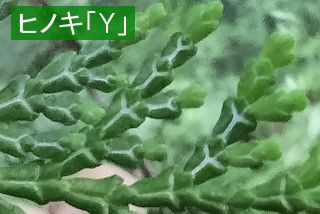
ヒノキ気孔「Y」
|

アスナロ気孔「W」
|

サワラ気孔「X」
|

クロベの葉裏
|
コシアブラとタカノツメ
どちらもウコギ科の落葉小高木で、コシアブラ(漉油)はコシアブラ属、タカノツメ(鷹の爪)はタカノツメ属です。コシアブラの若葉は強い香りとコクがあり、タラの芽と並ぶ山菜として有名です。タカノツメの若葉も山菜として食べられます。やせ地のやや乾燥した尾根に生えるこの2種の木は、葉で見分ける事が出来き、コシアブラは「葉は互生し、掌状複葉で5枚の小葉」、タカノツメは「葉は小葉が3枚集まった三出複葉」です。

コシアブラ
|

タカノツメ
|
なお、トウガラシの「タカノツメ(鷹の爪、ナス科)」とこの樹木の「タカノツメ」は全くの別物です。木のタカノツメは、冬芽が鳥の「鷹の爪」に似ていることから名づけられたと言われています。

唐辛子ではない
|

タカノツメの冬芽
|
ページ先頭(砺波市:頼成の森)へもどる。
Copyright © 2006-2025 Ikomaike TAKAOKA. All Rights Reserved.